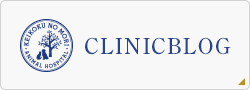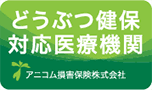2025/07/06
こんにちは。世田谷区等々力にありますけいこくの森動物病院です🌳
「避妊手術をしたはずなのに、なんだか様子がおかしい…」
「甘えたがりになって、大きな声で鳴いたり、オスの子に寄ってこられたり…」
そんな時、もしかすると【卵巣遺残症候群(らんそういざんしょうこうぐん)】という病気が関係しているかもしれません。
これは、避妊手術後に卵巣の一部が体の中にまだ残っていて、再び発情のような様子が見られる病気です。
◆ 卵巣遺残症候群ってなに?
「卵巣遺残症候群(Ovarian Remnant Syndrome:ORS)」とは、避妊手術のあとに卵巣の組織が少し残ってしまい、その部分からホルモンが分泌されることで、また発情のような行動が出てくる状態をいいます。
避妊手術は本来、左右の卵巣を取り除いて発情や妊娠、病気を未然に防ぐために行います。
しかし、手術のときに卵巣が全部取りきれていなかったり、ほんの小さな一部が残ってしまっていたりすると、体が「まだ卵巣がある」と判断して、発情に似た反応が出てしまいます。
◆ どんなサインが出るの?
「避妊手術をしたのに、なんで…?」
そう感じるきっかけとなる症状には、次のようなものがあります。
▼ わんちゃんの場合
- 陰部がふくらんだり、出血が見られる
- そわそわして落ち着かない様子
- マウンティング(ほかの犬や人に乗るような行動)
- オス犬が強く興味を示してくる
- 乳腺が張っている
▼ ねこちゃんの場合
- 大きな声で鳴く(いわゆる“発情鳴き”)
- 地面に体をこすりつけたり、くねくねと動いたりする
- 尾をピンと上げて、おしりを突き出すような仕草
- 何週間かおきに、こうした様子が繰り返される
- 乳腺が張っている
こうした行動が手術後にも何度か見られるようであれば、「卵巣が残っているかも?」と疑ってみる必要があります。
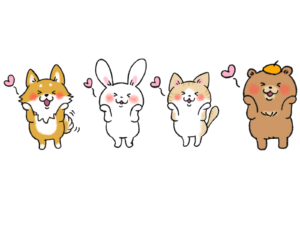
◆ どうして卵巣が残ってしまうの?
もちろん、手術では卵巣を完全に取り除くことを目的としています。
でも、実は次のような理由で、取りきれずに残ってしまうことがあるのです。
卵巣が見えにくい場所にある
個体差があり、卵巣が深い場所や腎臓の近くにあると、見つけにくいことがあります。
脂肪や癒着で隠れている
手術中に脂肪に包まれていたり、過去の炎症で癒着していたりすると、視界が悪くなることも。
出血や緊急手術などで状況が悪い
急ぎの手術や、出血が多くて視界が悪いときには、完全に確認できないこともまれにあります。
まれに卵巣片が腹腔内に落ちて残ることも
術中にごく小さな卵巣の断片が体内に落ちて、それが生き残り、ホルモンを出し続けることもあります。
◆ どうやって調べるの?
卵巣遺残症候群かどうかは、いくつかの検査を組み合わせて判断します。
見た目や行動だけでは、はっきりとはわからないことも多いため、丁寧な診断が必要です。
行動や症状の聞き取り
発情のような様子が、いつ・どれくらいの間隔で出ているのかを確認します。
血液検査(ホルモン値の測定)
エストロゲンやプロゲステロンなど、性ホルモンの数値を測ることで、体の中に卵巣の働きが残っていないかを調べます。
※ 発情中に検査を行うと、より正確な結果が出やすいです。
おなかのエコー検査(超音波検査)
卵巣のような組織が見えるかどうかをチェックします。脂肪や小ささで見えないこともあります。
ホルモン刺激検査
ホルモン剤を注射し、体の反応を調べることで、卵巣があるかどうかを判断します。
CT画像検査
CT画像検査を行うことにより、エコーより詳細な確認ができます。
当院ではCTがないため、専門病院へご紹介させていただきます。
確定診断は開腹手術での確認
どうしても確定できないときには、お腹を開いて卵巣の残りを探す「探索手術」が必要になることもあります。
◆ どうやって治すの?
この病気の治療は、残っている卵巣の組織をきれいに取り除く再手術です。
事前の検査で場所のおおよその見当をつけてから、お腹の中を丁寧に確認し、卵巣の残りを探してしっかり取り除きます。
再手術の特徴
- 通常の避妊手術より、少し難易度が高いです
- 卵巣の位置が深かったり、小さな断片になっている場合もあります
- どんなに小さな組織でも、ホルモンを出す可能性があるので、見逃しのないよう慎重に確認します
◆ 手術のあとは?
再手術で卵巣の遺残を取り除ければ、ほとんどの場合、発情のような症状は見られなくなります。
ただし、手術後しばらくは、体に残っていたホルモンの影響で、発情様の行動が一時的に続くことがあります(1〜2週間程度)。
また、片方の卵巣を見つけた場合でも、反対側にもう一つ残っていないか確認することが大切です。
◆ 放っておくとどうなるの?
卵巣が残ったままになっていると、次のような病気のリスクが高くなる可能性があります。
- 乳腺腫瘍(特にわんちゃんでの発症リスクが高まります)
- 子宮の一部が残っていた場合は、子宮蓄膿症など
- 発情によるストレスや体調不良
早めに気づいて治療を行うことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
◆ 予防のためにできること
卵巣遺残症候群を防ぐには、最初の避妊手術で卵巣をしっかりと取り除くことがとても大切です。
▼ 飼い主さんにできること
- 手術経験が豊富な病院で手術を受ける
- 術後も愛犬・愛猫の行動をよく観察する
- 「ちょっと変かも」と思ったら、遠慮せずに相談する
当院では再手術にならないよう、避妊手術の際に取り除いた卵巣・子宮を確認し、しっかりとした術後管理を行っています。
◆ まとめ|「手術したのに変だな?」と思ったら、まずご相談を
避妊手術をした子が、また発情のような行動をするのは、ちょっと不思議ですよね。
でも、それは「卵巣遺残症候群」という病気のサインかもしれません。
この病気は、正しく診断して適切に治療すれば、きちんと治る病気です。
飼い主さんが「おかしいな?」と気づいてくださることが、なによりの第一歩になります。
気になる症状があるときは、どうか迷わずご相談ください。
大切なご家族が、ずっと元気に過ごせるように、一緒にサポートしていきます。
東京都世田谷区、等々力、玉川、上野毛、尾山台、自由が丘、田園調布で、お困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
。・゚・。。・゚・。。・゚・。。・゚・。・゚・。
けいこくの森動物病院 世田谷犬猫歯科
〒158-0082
東京都世田谷区等々力1-34-18
シュロス等々力1F
TEL:03-3704-1014
。・゚・。。・゚・。。・゚・。。・゚・。・゚・。